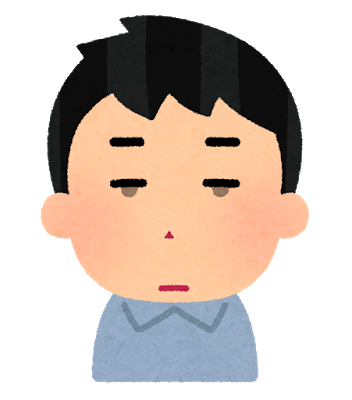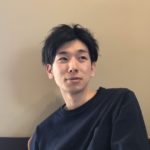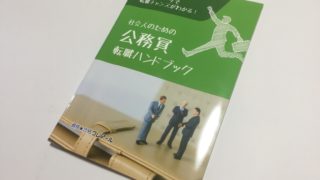こんにちは!元公務員のHiroshiです。
でもやっぱり辞めるのはなかなか踏ん切りがつかないし、どうすれば良いんだろう…
転職も考えているけど、できるのか不安だ。。
安定の代名詞的な職業で、就職先として人気の「公務員」。
しかし新卒で公務員になっても、1年目で「辞めたい」と思う人も珍しくありません。
かく言う僕もその1人。
新卒で県庁に入りましたが、違和感がぬぐいきれず、結局2年で退職しました。
この記事をご覧のあなたと同じく、新卒で公務員になり、辞めたいと悩んでいました。
今回は「公務員を辞めたい新卒職員はどうすべきか」に関して、僕の経験から話します。
先に結論を言うと、最初に「理由」を整理すべきです。
そして、その理由が「辞めるべきパターン」に該当したら、即行動が正解です。
本記事で、いま抱えている悩みが解消に近づき、明るい日々につながるはず。
3分ほどで読めるので、ぜひ最後までお付き合いください。
【はじめに】公務員の新卒1年目はきつい。後悔するのも普通です

まず始めに「公務員の新卒1年目は普通にきつい」という話をします。
公務員1年目で辞めたいと思っている方は、何かしらキツいと思っている部分があるはず。
でも、きついのは別にあなただけではありません。
(僕も普通にきついなと思っていました)
その理由は、公務員特有の事情にあります。
- 縦割りの業務
- 新人は放置されがち
- イメージとのギャップが大きくなりやすい
それぞれ解説していきます。
①:縦割りの業務
公務員の仕事は完全な縦割り。
同じ部署でも、個人によって業務が細分化しています。
- A係長→〇〇事業に関すること
- B主任→△△事業に関すること
- C主事→□□事業に関すること
例として上記ですね。
1年目の新人も同様で、いくつかの業務の主担当になります。
つまり、最初の段階から前任者と同じレベルの仕事が求められるんです。
でも冷静に考えて、1年目の最初から仕事を自分でこなせるわけがありません。
右も左も分からない状態なので当然ですね。
隣の席の人は自分と全く違う業務を行っているので、誰かに聞くのも難しいです
自ずと、自分でやりながらなんとか頑張るしか選択肢はありません。
そりゃ「しんどい」と感じますよね…
一方で、他の民間企業等だと全然変わってくるはず。
- 入社してしばらくは研修
- 配属後も先輩社員からサポートが受けられる
研修なんて無いに等しい公務員は違い、手厚く育ててもらえるでしょう。
(民間に行った僕の友人も、みんな数ヶ月の研修を受けていました)
総じて、公務員は1年目から即戦力として仕事をするのが求められます。
加えて、教えてもらえる環境にもありません。
どうしても最初は「きつい…」と感じてしまいますね。。
②:新人は放置されがち
公務員1年目が放置されるのもあるあるです。
理由は先ほどの縦割りの話にも関連しますが、以下ですね。
- みんな忙しい→新人にかまっている余裕がない
- 業務内容が全然違うので、自分の業務に関して周りも知らない
- 上司も異動してきたばかりだと、業務に関する知識がなくて大変
忙しさ・仕事のやり方・異動などの事情ゆえに、放置されやすいのかなと思います。
新人なのに放置されていると、かなり辛い気持ちになります。
何をやればいいのか分からないと不安ですし、暇でやることがないのも、それはそれで辛いです。
やることが分からない&周りにも聞かない状態でいたら、自分の業務が実は大変な事態になっていることも。
公務員の仕事の流れが分からない状態で放置されるのは、大きな不安が募りますよね…
③:イメージとのギャップが大きくなりやすい
入庁前は、公務員に対して良いイメージを持つ方が多いはず。
しかし現実とイメージは結構違うので、そのギャップに苦しむ場合も多いです。
- 残業が少ないと思っていた
→激務部署に配属され、連日残業が続いている - 有給が取りやすいと思っていた
→仕事が忙しすぎて休みが取れない - チームで働くと思っていた
→完全に個人プレイで心細い
例えば上記のとおり。
特に公務員はインターン等もショボく、事前に職場を体感することが難しい職業。
また部署ごとにも忙しさ・有給・残業の考え方などが全然違います。
加えて大半の人が、安定・なんとなくのイメージ・家族のすすめ等の理由で公務員になっています。
必然的に、入庁前と入庁後でギャップが生まれる→後悔につながりやすいんです。
【新卒1年目の公務員へ】まずは辞めたい理由を整理すべき

上記のとおり、公務員1年目は普通にきついです。
後悔したり、辞めたいと思っても全然不思議ではありません。
では、1年目で辞めたいと思ったら、公務員を辞めるべきなのか。
他のサイト等では「すぐに辞めろ」的なものが目立ちますが、僕はそうは思いません。
まずはあなたが辞めたい理由を整理すべきです。
辞めたい理由を深掘りすると、おそらく以下のパターンに分かれると思います。
- 人間関係や残業時間=職場環境に疲弊している場合
- 仕事が向いていない・できないと思う場合
- 「公務員の仕事」に違和感があり、合わないと感じる場合
- やりたいことができた場合
それぞれ「辞めるべきか辞めないべきか」お話しします。
①:人間関係・残業時間に疲弊している場合
1つ目のパターンが、職場の人間関係や残業時間の多さによる場合。
- いまの上司と合わず、パワハラまがいの状況にある
- 残業が多くて、精神的につらい
上司との関係や残業時間等が理由なら、まだ公務員を辞めない方が良いです。
なぜなら、それは異動すれば解消される可能性が高いから。
あなたが辛いのは「公務員の仕事」そのものではなく、今の「環境」だと思います。
それは単純に、配属先の運が悪かっただけです。
せっかく努力して公務員試験に受かったんです。
1つ目の職場が合わなかったために、あなたが公務員を辞める必要はありませんよ。
また、本当に辛いのであれば療養休暇(病気休暇)を取得しましょう。
療養休暇を取得すれば、休みながら給料を満額もらえます。
復帰後には業務量に配慮してもらえたり、上司または自分が異動したりします。
こんな心配をする方もいるかもしれません。
でも、1人いなくても組織は何事もなく回ります。
まして新人が抜けても影響はごく小さいものです。
(逆に新人ひとりが抜けて機能しなくなるのは組織として終わってます)
療養休暇を取ればかなり時間ができるので、今後について考える時間もできますよ。
続けるか辞めるかの判断も含めてじっくり考えられるので、いずれにせよすぐに辞める必要はないです。
※療養休暇の取得については、公務員の療養休暇の取り方を解説で詳しく書いています。
②:仕事が向いていない・できないのが辛い場合
多分向いていないんじゃないかな…
「仕事ができない→向いてないから辞めたい」と思う場合もあるかもしれません。
ただ、この場合もまだ辞めない方が良いかと。
そもそも、新卒1年目で仕事ができないのは当然です。
社会人経験もない上、役所の仕組みもきちんと分かっていないんですから、できる方が不自然です。
前述のとおり、公務員1年目の仕事は状況的に難しいですし。
また、おそらく上の人達も「最初からできる」とは思っていないはず。
「できないこと=悪いこと」とは思わず、徐々に慣れていけば問題ナシですよ。
1年目のうちから、仕事ができないことに悩む必要はありません。
「できないことは悪いことじゃない」と考えて、気楽に頑張ってみてください。
③:「公務員の仕事」に違和感を抱いている場合
3つ目のパターンが、「公務員」そのものに違和感を抱いている場合です。
- 業務の大半が「仕事のための仕事」でやりがいが持てない
- 仕事の中で無駄が多すぎる
- 巨大組織で仕事をするのが合わない・しんどい
- 自分の持っている価値観と行政の仕事が合わない
例をあげるなら上記のとおり。
つまり、公務員の仕事や行政組織そのものに違和感・疑問を抱いている場合です。
このような方は、早めに公務員を辞めるべきです。
ちなみに僕もこのパターンで、公務員の仕事と自分の価値観が合わず、苦しんだのを覚えています。
このパターンの方は、ぜひこのまま読み進めていただけたらと思います。
④:やりたいことができた場合
やりたいことができたなら、すぐにでも辞めた方が良いです。
やりたくもない公務員の仕事をするより、やりたい仕事をした方が確実に幸福度が高いはず
特に新卒1年目なんて超若いですからね。
失敗してもやり直せるので、やりたいことにはどんどん挑戦すべき。
公務員を辞めたい新卒1年目は、すぐ辞めるべき理由
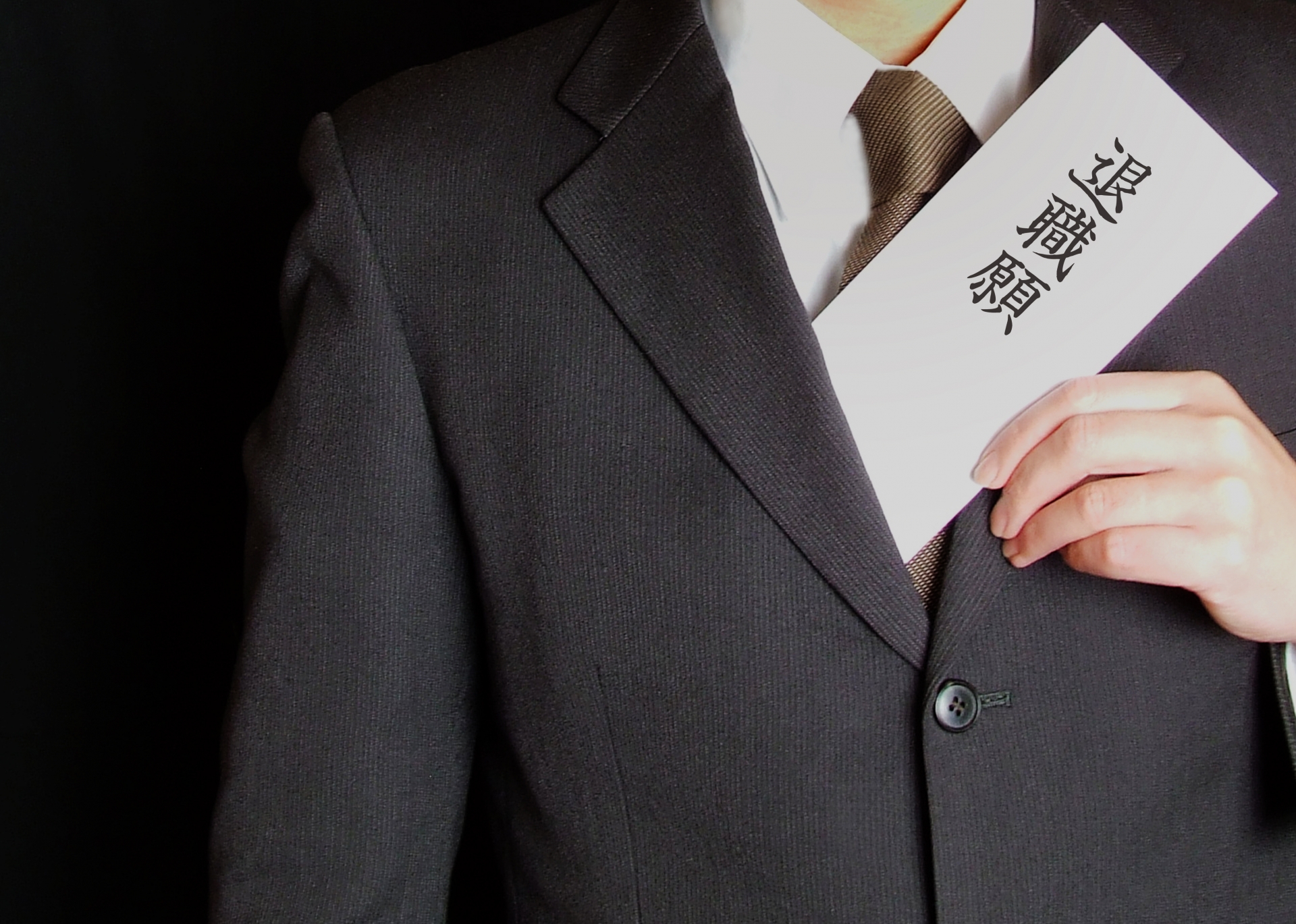
やりたいことがある方・公務員に違和感がある方は、早めに公務員を辞めるべき。
その理由は以下の3つです。
- 若い方が圧倒的に辞めやすい
- 仕事を続けても違和感が消えることはない
- 嫌な仕事を長年続けるのはしんどいし、もったいない
(辞めたい主な原因が「人間関係」などの場合も、公務員の仕事に違和感があるなら辞めるのを検討すべきだと思います)
理由①:若い方が圧倒的に辞めやすい
1つ目の理由は「若い方が辞めやすいこと」です。
これは2つ意味があり、1つが心理的なもの、もう1つがキャリア的なものです。
若い方が心理的に辞めやすい
新卒1年目なら、おそらく背負うものはかなり少ないはず。
養う家族がいる等も特にない方が多いと思います。
つまり、あらゆる選択権が自分だけにあるんです。
でも、年を重ねると状況が変わってきます。
- 結婚して家族ができる・子どもが生まれる
- 両親がリタイア。介護が必要になることも
上記のようになると、自分以外のことを考える必要が出てきます。
自分だけの問題ではなくなるので、明らかに身動きが取りにくくなるはず。
必然的に、辞める心理的なハードルがグッと上がるのは間違いありません。
つまり新卒1年目のいまが、あなたの人生の中で最も心理的に身軽で辞めやすい時です。
若いうちなら転職しやすい
もう1つの「キャリア」について。
ご存知かもしれませんが、公務員は年を重ねるごとに転職市場では厳しくなります。
公務員の仕事の性格上、利益を上げる思考に乏しく、民間企業では「使えない」と見なされるためです。
割とよく聞く話ですよね。
でも、20代の若手ならば話は別。
若手ならば公務員に染まっておらず、企業側も再教育ができると考えるためです。
転職市場においてもさほど不利になりません。
まして、新卒1年目ならば「第二新卒」として転職することも可能。
むしろ「公務員試験に受かるだけの能力・地頭がある」とプラスに捉えられることもあると聞きます。
年齢を重ねた場合に比べて、キャリア的にも明らかに公務員を辞めやすいです。
理由②:仕事を続けても違和感が消えることはない
いまあなたは、公務員の仕事に対して何らかの違和感を持っていると思います。
そして、その違和感は今後も消えることはありません。
当然といえば当然ですよね。
行政組織の仕事のやり方や性格は、絶対に変わらないんですから。
そして公務員の仕事を続けていくと、良くも悪くも「慣れ」が出てきます。
環境に慣れて、人間関係も固定化されていくと、間違いなく辞めにくくなります。
将来、ある程度の年齢に達した時を想像してみてください。
「自分のいる場所はここじゃない」と思うこともあり得ますよね。
その時には、心理的にもキャリア的にも辞めることは非常に厳しい状況になっています
間違いなく、残りの人生を我慢しながら働いて過ごすことになるはず。
確かに、「慣れ」で一時的にごまかすことはできます。
しかし、新卒時に感じた違和感を完全に消し去ることはできません。
大半の場合で直感は当たりますし、自分の中に残り続けます。
違和感を我慢しながら仕事をする人生は、多分幸せではありません。
それなら、選択肢の多い若手のうちに環境を変える選択をした方が賢明です。
理由③:嫌な仕事を長年続けるのはしんどい&もったいない
あなたが違和感を抱いている公務員の仕事を、これから40年続けると想像してください。
絶望的な気分になりませんか?
僕は2年目のときに、自分の価値観と公務員の仕事が合わないと気づきました。
この時は公務員として仕事をすることにいつも絶望していましたね。
仕事は人生の中で結構な割合を占めるものです。
違和感を覚えながら仕事を続けていくのは、本当につらいと思います。
確かに公務員は安定しているかもしれません。
しかし、安定を理由に自分に合わない仕事を我慢して続けて、果たして幸せでしょうか?
自分が力を発揮できる環境を見つけて、そこで頑張った方が絶対に幸せです。
新卒のあなたのこれからの人生は長いです。
そして、公務員以外のキャリアの可能性だってまだまだあります。
合わない仕事で疲弊し続けるのは、人生の充実度を考えると超もったいないです。
新卒1年目で公務員の違和感を気づけた人はラッキー

公務員を辞めたい新卒1年目の人は、自分に対して否定的に思いがち。
僕も県庁にいたから分かりますが、公務員を辞める人はかなり少ないです。
同期の大半がちゃんと仕事をしていますし、最後まで勤め上げる雰囲気もあります。
でも今になって思いますが、新卒1年目で違和感に気づけた人は逆にラッキーですよ。
- 違和感に従って若いうちに方向転換
→違う分野で成果を出せる可能性が高まる。時間の自由もある - 違和感に気づくのが遅くなる
→辞めるハードルが上がる。疲弊しながら何十年も働く
早くから違和感に気づけたことはマイナスなことではなく、むしろプラスなことです。
何事においても同じですが、悪い面ばかりではありません。
公務員を辞めたい新卒1年目の人は、即行動しよう

このように感じている人が多いかもしれませんが、その理由は1つです。
それは行動していないから。
何もアクションを起こしていない状態で、やりたいことが降ってくるなんてあり得ません。
「始めてみたら面白くて、もっとやりたいと感じる」のが自然な流れです。
おそらく多くの方が普段の業務に手一杯で、同じ日々を過ごしているだけだと思います。
それではやりたい仕事になんて出会えませんし、他の仕事ができる自信も出ません。
単純に、公務員の仕事にしか触れていないわけですからね。
まずは公務員である今のうちから、なにかしら行動を始めるのがおすすめです。
公務員を辞めたい新卒1年目が、絶対にするべき「行動」とは

おすすめの行動を大きく分けて2つご紹介します。
それは「スキルアップ」と「転職活動」です。
①:スキルアップ
1つ目が「スキルアップ」です。
スキルアップといっても、別に公務員の仕事に関するスキルではありません。
ここで言う「スキルアップ」とは、普遍的な価値のあるスキルです。
例えば以下のようなもの。
- プログラミング
- Webデザイン
- Webマーケティング
- Webライティング
- 動画編集・映像制作
これらは専門的で普遍的、つまり市場で評価されるスキル。
しっかりと身につけることができれば、自分の価値も上げやすいです。
ちなみに、この辺のスキルアップは僕も取り組んできました。
以下の記事にて詳しく紹介しているので、ぜひやってみてください。
②:転職活動
2つ目が「転職活動」です。
視野を広げる・やりたいことを見つけるには、転職活動で新しい可能性を探すのがおすすめ。
色々と話を聞いているうちに、興味のある仕事が見つかるはずです。
会社に入れば、価値の高いIT系のスキルを、給料=お金をもらいながら学べます。
仕事の中でスキルが身につかない公務員とは全然違いますね
新卒の公務員であれば、前述のとおり「第二新卒」として転職もしやすいです。
若いほどにチャンスがありますので、ぜひ動いてみましょう。
具体的な転職活動について
転職エージェントを利用するのがおすすめ。
希望に沿った企業の紹介や面接対策などの手厚いサポートが無料で受けられます。
転職エージェントは色々ありますが、最大手のリクルートエージェントが鉄板。
案件数・サポートの質ともに非常に高水準。
かなり評判が良く、あなたが輝ける環境が見つかるはずです。
※転職活動にハードルを感じる方は、転職サイトのリクナビNEXTがおすすめ。
エージェントと違って面談は特にありません。
自分のペースで少しずつ転職活動を始められます。
色々な仕事を見て情報収集するだけでも、間違いなく視野は広がるはず。
良いと思った案件を、リクルートエージェントの担当につないでもらうこともできます。
新型ウィルスの影響が心配されますが、Web通話や電話でも相談可能です。
直接オフィスに行く必要はないので安心ですね。
【まとめ】仕事を辞めたい新卒公務員は、すぐに行動して退職するべき

「仕事を辞めたい新卒の公務員はどうすべきか」を書きました。
記事で書いたとおり、「違和感に気づいたら公務員を辞めるべき」です。
「石の上にも3年」なんて言うのは老害だけです。
違和感を持ったまま続けても何にもならないので、スパッと次に行きましょう。
キャリア的なこと・心理的なことから、あなたが公務員で居続けるメリットはありません。
ただ、やはり「何もない状態ですぐに辞めるのは怖い」と思います。
急に辞めると収入も途切れますし、一気に無職ですからね。
恐怖や不安を抱いて当然ですよ。
それなら、在職中である今から新しい行動をするのがおすすめです。
公務員である「今」動けば、リスクを減らした状態で次への準備ができます。
- スキルアップの勉強:仕事が取れる状態まで学ぶ
- 転職活動:内定を取り、転職先を決めてしまう
退職後を見越して動けば、恐怖はかなり取り除かれるはずです。
確かに、仕事をしながらの行動は少しキツいかもしれません。
しかし、転職サイトを昼休みでも見られますし、有給を使えば転職活動も可能です。
スキルアップの勉強は、平日の仕事終わり・休日を利用してゴリゴリ頑張ればいけます。
結局、すべて自分がやるかどうかです。
新卒のあなたのこの先は長いです。
自分のやりたいことを見つける行動をするか、この先も違和感を抱きながら・文句を言いながら公務員を続けていくか。
このままページを閉じても、悩み続けるだけだと思います。
未来を変えたいと思うのであれば、ぜひこの機会に新しく行動してください。
【無料】おすすめの転職サイト・転職エージェント
- リクルートエージェント
:転職エージェント。企業の紹介・面接指導などのサポートを受けられる。
リクナビNEXT:超大手転職サイト。案件数も多く、情報収集に最適。
※いずれも登録は3分ほどです
※こちらの記事にて、公務員におすすめの転職サイトを詳しく比較しているので、あわせてご覧ください。

行うべきスキルアップの勉強
https://public-allabout.com/koumuin-skill-up/