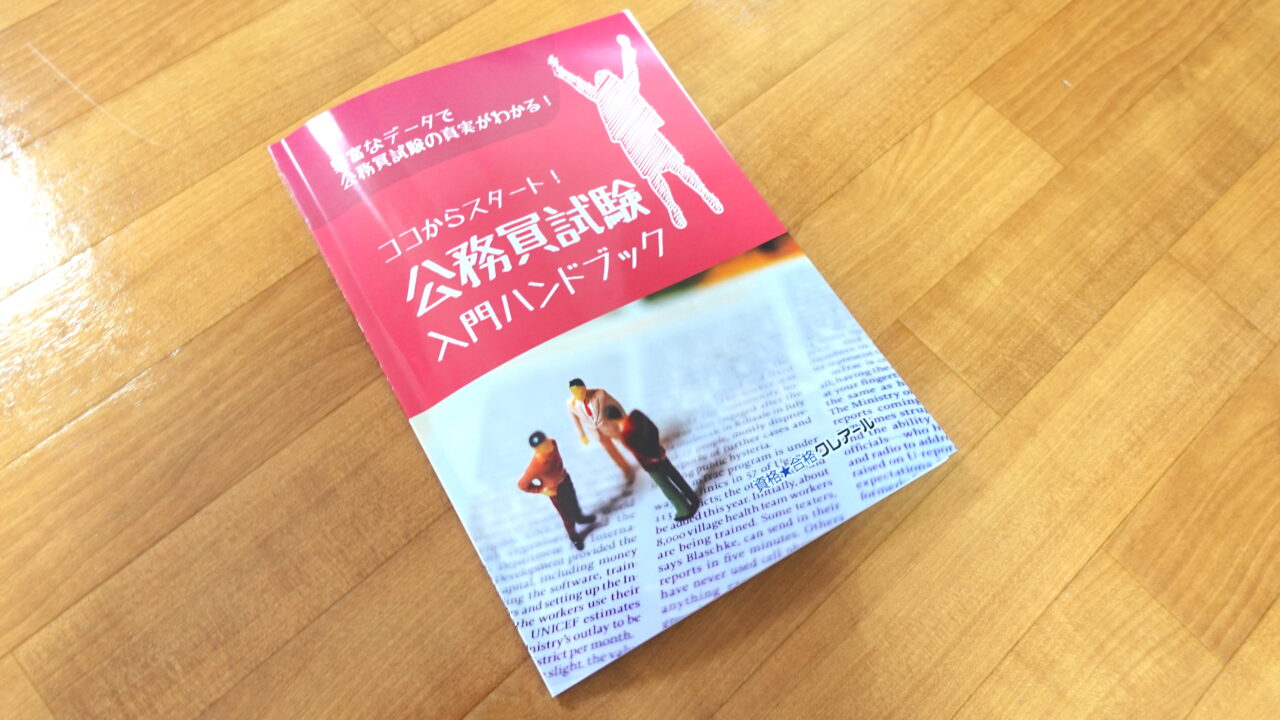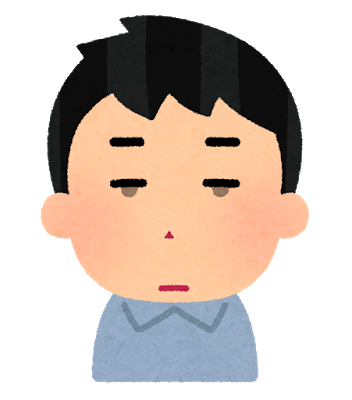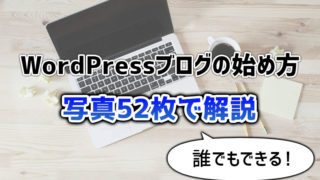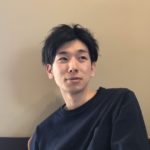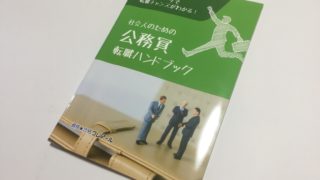こんにちは!元公務員のHiroshiです。
「公務員になりたい」と思ったあなたは、次のような状況ではないでしょうか?
- 1日でも早く勉強を始めようと考えている
- どんな参考書を買えばいいのか悩んでいる
- とりあえず「〇〇県用」と書かれた問題集を買った
しかし断言しますが、上記はすべてNG行為です。
最悪、公務員試験合格できなくなるかもしれません…
その理由は、最初にやるべき段階を飛ばしているからです。
そこで今回は「公務員になりたい人が最初にやるべきこと」を解説します。
ちなみに僕は、県庁で働いていた経験を持つ元公務員です。
YouTubeでも、公務員試験に関する情報を発信しています。
登録者が1.8万人ほどおり、多くの視聴者の方が合格しました。
本記事を読むことで、公務員試験対策の正しい手順が分かり、合格の確率が上がります。
3分ほどで読めるので、ぜひ最後までお付き合いください。
【大学生が公務員になるには】まずは情報収集から行うべき理由

公務員になりたい大学生の方は、まずは「情報収集」から始めてください。
大事なことなのでもう1度言います。
とにかく「情報収集から」です。
いきなり勉強をしても、それはゴールのないマラソンだからです。
公務員試験は、非常に長丁場の試験です。
試験科目が多く、筆記・面接・論文などたくさん課されます。
効率的に攻略していくには、情報を得て正しい対策を行うことが不可欠です。
- どんな科目が出るのか
- 試験の出題形式や配点はどんな感じか
- 論文や面接では何が問われるのか
- 試験のスケジュールはいつか
まずは上記の情報を得る。
そして「いつまでに何をできるようにすればいいか」を逆算して考えることが必須です。
一方、十分な情報収集をせずに勉強をスタートさせたらどうなるか?
- 行き当たりばったりの勉強になる
→試験までに必要な勉強が終わらない可能性 - 配点を意識した勉強ができず、重要でない箇所を勉強する
→無駄な努力をしてしまう
上記の状況に陥るのは本当にあるあるです。
正しい目標設定ができないんですから、成果も出ません。
つまり、情報収集しないとシンプルに落ちるんです。
情報収集→正しい目標設定ができなければ、非常に高い確率で失敗します…
公務員になりたい大学生が知っておくべき内容

では具体的にどんな情報を知っておくべきなのか。
それは「試験の全体像」です。
具体的には、主に以下の3点です。
- 公務員の仕事の中身や職種
- 試験の内容・出題される科目
- どんな問題が出るのか
それぞれ解説していきます。
①:公務員の仕事の中身や職種
ひとことで「公務員」と言っても、非常に幅広いです。
「自分は何の公務員になりたいか」を決めるために、職種や仕事の概要はチェックしておきましょう。
- 地方公務員(行政or技術)
→都道府県庁・政令市・市役所・町役場など - 国家公務員(行政or技術)
→総合職・一般職 - 国家専門職
→国税専門官・財務専門官・労働基準監督官など - その他の公務員
→警察・消防など
一例を挙げておきました。
上記のような方もいると思います。
ただそれでも、職種や仕事内容は把握しておくべきです。
- よく分からない状態だと、入庁後に苦しむ可能性がある
→「こんなはずじゃなかった」と退職することも - 併願先を決めるため
→公務員試験は併願をするのが普通
特に「併願先」ですね。
併願先は、第一志望の受験科目や仕事への興味で決めるものです。
職種や仕事内容を把握していないと、良い併願先選びができなくなります。
まずが職種や仕事内容を知って、自分の目標を決める。
これが「公務員になりたい人」にとってのスタートです。
②:試験の内容・出題される科目
受ける自治体・試験をなんとなく決めたら、次は試験の中身です。
- 課される試験の内容:教養のみor専門あり
- どんな科目が課されるか
- 2次試験の形式:論文試験・面接試験
上記はチェックしておきましょう。
試験の中身を知っておかないと、正しい対策は絶対にできません。
「何をどれくらい勉強する必要があるのか」が把握できないと、行き当たりばったりの勉強になります。
科目や配点から、合格のために必要な勉強を考えることが必須。
自分の受ける予定の試験のスケジュールも併せて確認しておきましょう。
③:どんな問題が出るのか
さらに、具体的に「どんな問題が出るのか」もチェックすべき。
今の自分の肌感覚を知るためです。
ザッとでも問題を見ておくことで、以下が分かります。
- 今の自分でどれくらい分かるのか
- どの程度までレベルを引き上げればいいのか
- 試験までの残りの期間で本当にできそうか
なんとなく「合格までの距離」が掴めるんですよね。
そして得た情報を元に、勉強方法を決定していきます。
具体的には「独学なのか予備校なのか」です。
どんな勉強が必要で、現在の自分でどの程度なら分かるのか。
さらに自分の性格などを踏まえて判断していく形です。
正しい道筋を立ててしっかり勉強すれば、独学でも予備校でも合格は可能です。
「公務員試験入門ハンドブック」で、必要な情報収集は完了します
ここまで読んで、上のように感じた方もいるはず。
書籍やインターネットで自分で情報収集するのは、本当に途方もない作業です…
しかし「公務員試験入門ハンドブック」があれば一発で完了します。
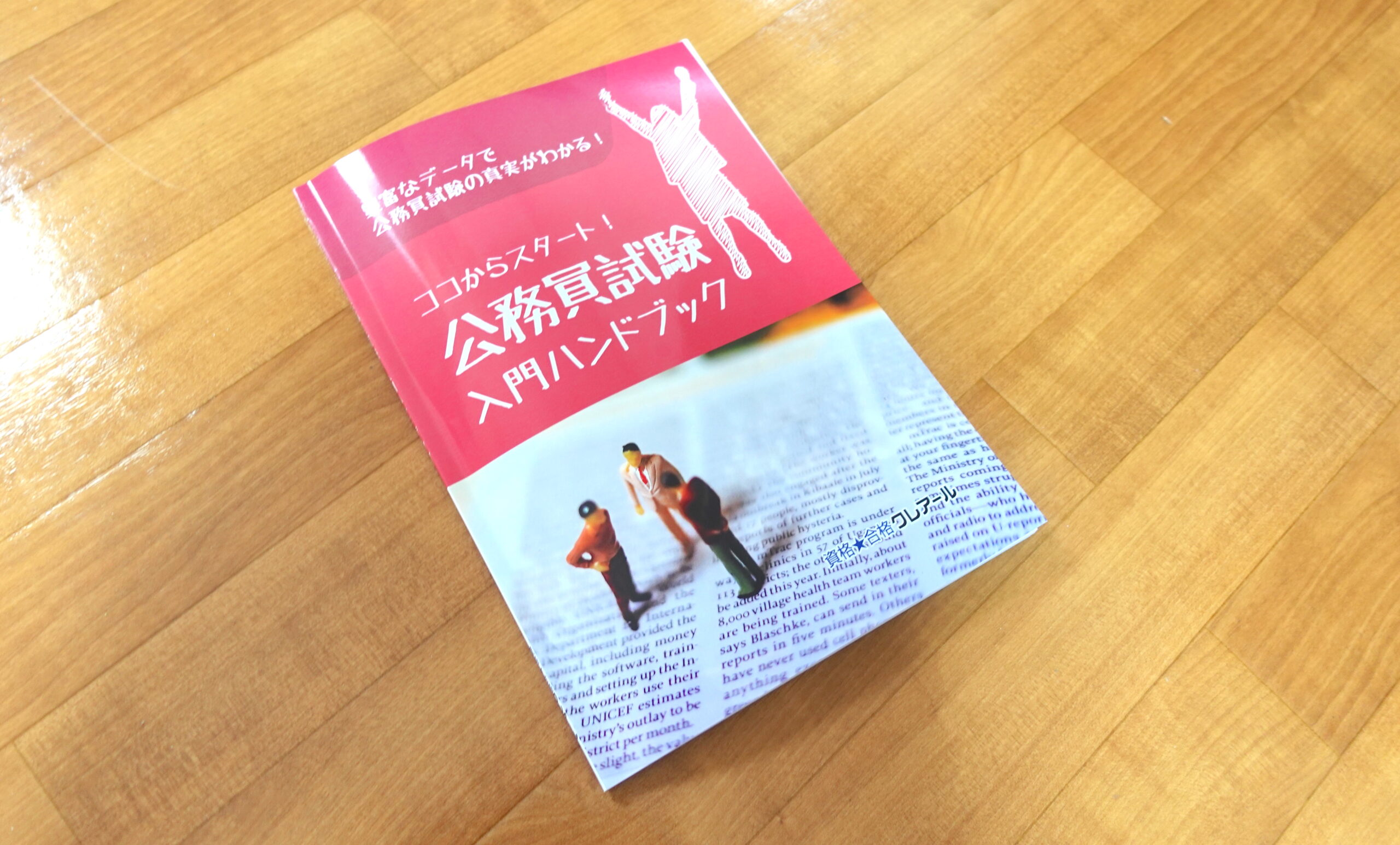
こちらは、公務員予備校のクレアールが無料で配布している冊子です。
(クレアールはWeb通信に特化した予備校です)
全部で88ページあり、内容としては以下です。
- 公務員の種類や仕事内容
→国家公務員・地方公務員のほとんどを網羅して紹介 - 採用区分と職種
→各試験の受験資格やスケジュール - 公務員試験ガイド
→科目や例題の紹介。学習プランの立て方など - その他のよくある悩みについて
→みんなが気になる疑問への回答・合格体験記
僕も読みましたが、これ1冊で公務員試験の全体像を網羅しています。
大手予備校のクレアールが作っているからこそ、情報も非常に質が高いですよ。
(紙も良質で、普通に1〜2,000円レベルのクオリティです)
※電話番号の入力は任意。しつこい勧誘なし
公務員試験入門ハンドブックのメリット

公務員試験入門ハンドブックのメリットを深掘りして紹介します。
- お金と時間を圧倒的に節約できる
- 勉強の指針になる
- 体験記が非常に参考になる
具体的には、上記の3点です。
①:お金と時間を圧倒的に節約できる
情報収集の手段は、一般的に書籍とネットの2種類です。
しかし、それぞれ以下のデメリットがあります。
- 市販の書籍:体系的に理解できるがお金がかかる
→1〜2,000円はかかる - インターネット:無料だが情報が断片的。理解に手間がかかる
→情報の信頼性の面でも懸念あり
情報収集は超大事ですが、お金をかけたくない方もいるはず。
また時間をかけるべきは、情報収集よりも「勉強」ですよね。
(たくさん勉強しないと合格はできないので)
「公務員試験入門ハンドブック」なら、書籍・ネットの欠点を補えます。
- 無料で手に入る
- 情報が体系的にまとまっている
大手予備校のクレアールが出しているので、情報の信頼性も◎
お金と時間を節約しながら、質の良い情報にアクセスできるんです。
②:勉強の指針になる
「何から手をつけるべきか分からない」方も多いはず。
このガイドブックの素晴らしい点は、学習の進め方の解説です。
公務員試験の特徴として、以下の3点があります。
- 科目数が非常に多い
- 配点が科目によってまちまち
- 6〜7割の得点で合格できる
そこで大事になるのが「勉強の戦略」です。
つまり「科目に優先度をつけながら勉強する」のが、合格の決め手になります。
公務員試験入門ハンドブックでは、その特徴に応じた最適な勉強方法を解説。
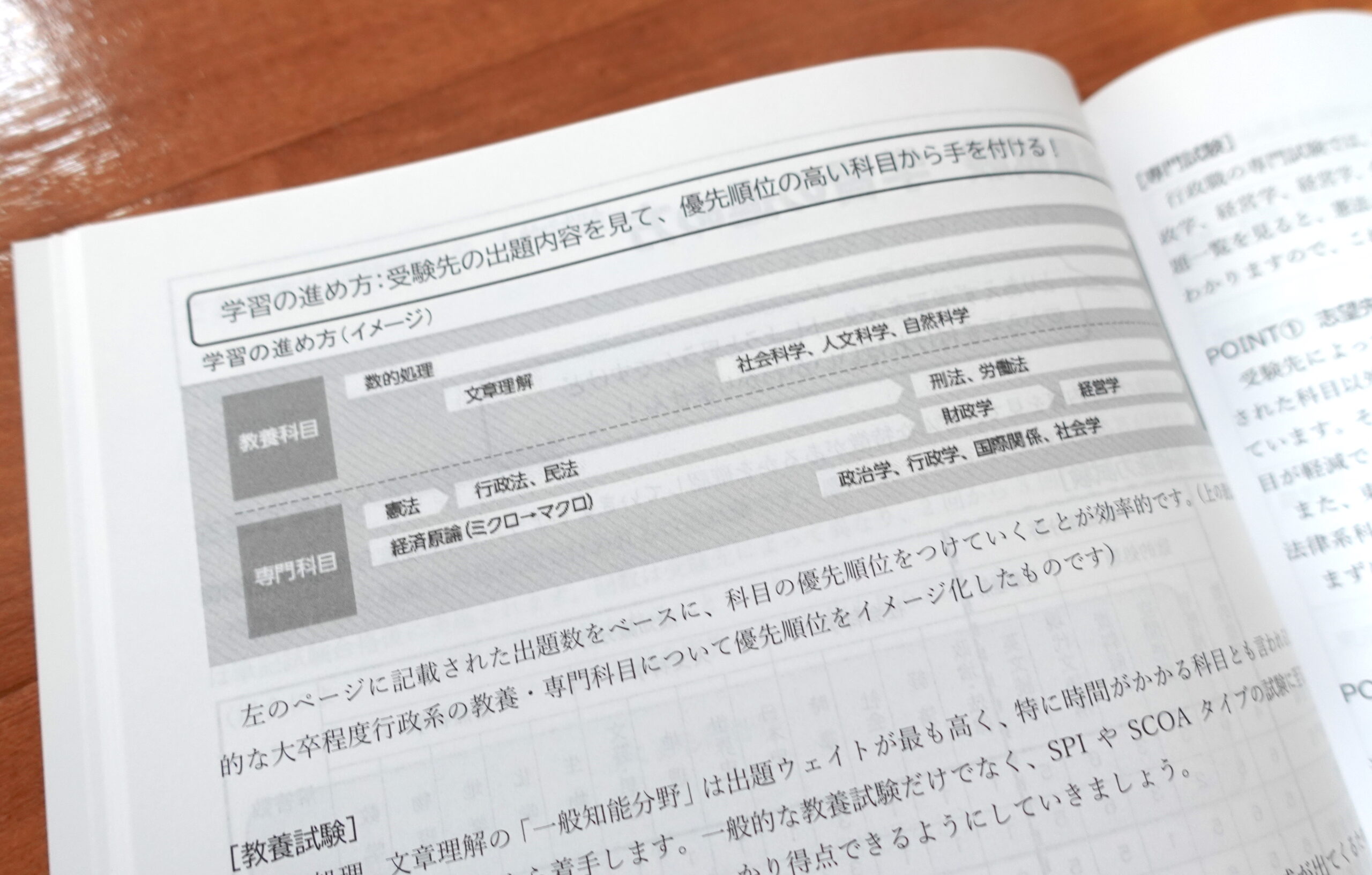
「何を優先的に勉強すべきか」「効率的な勉強の進め方」等が全部分かるんです。
独学・予備校を問わず、勉強する上での指針になってくれるはず。
勉強の仕方を間違うリスクは、この1冊で格段に減らせますよ。
③:合格体験記が読める
合格体験記も公務員試験入門ハンドブックの特徴の1つ。
特に「勉強で苦労したこと」がピックアップされています。
- 時間の使い方・学習の進め方
- 苦手科目の対策方法
- モチベーション維持の仕方
例えば上記ですね。
公務員試験の勉強をしていると、必ず壁にぶち当たります。
上記は本当にあるあるで、僕も辛かったです。
そんな時に役に立つのが「先人の知恵」なんですよね。
合格した人が「どうやって壁を乗り越えたか」を知り、それを実践することで、あなたも乗り越えられます。
悩むポイントは、どんな人でも似通っているものです。
体験記はたくさん載っているので、あなたの境遇に近い方がいるはず。
このガイドブックは、勉強前の情報収集のみならず、学習中も役立ちます。
長丁場の公務員試験を乗り越える上で、マストで手に入れるべきです。
※電話番号の入力は任意。しつこい勧誘なし
「公務員試験入門ハンドブック」をもらう手順
続いて「公務員試験入門ハンドブック」をもらう手順を解説します。
と言っても超簡単で、3分ほどで完了します。
①:公式ホームページにアクセス
こちらから、公式ホームページにアクセスしてください。
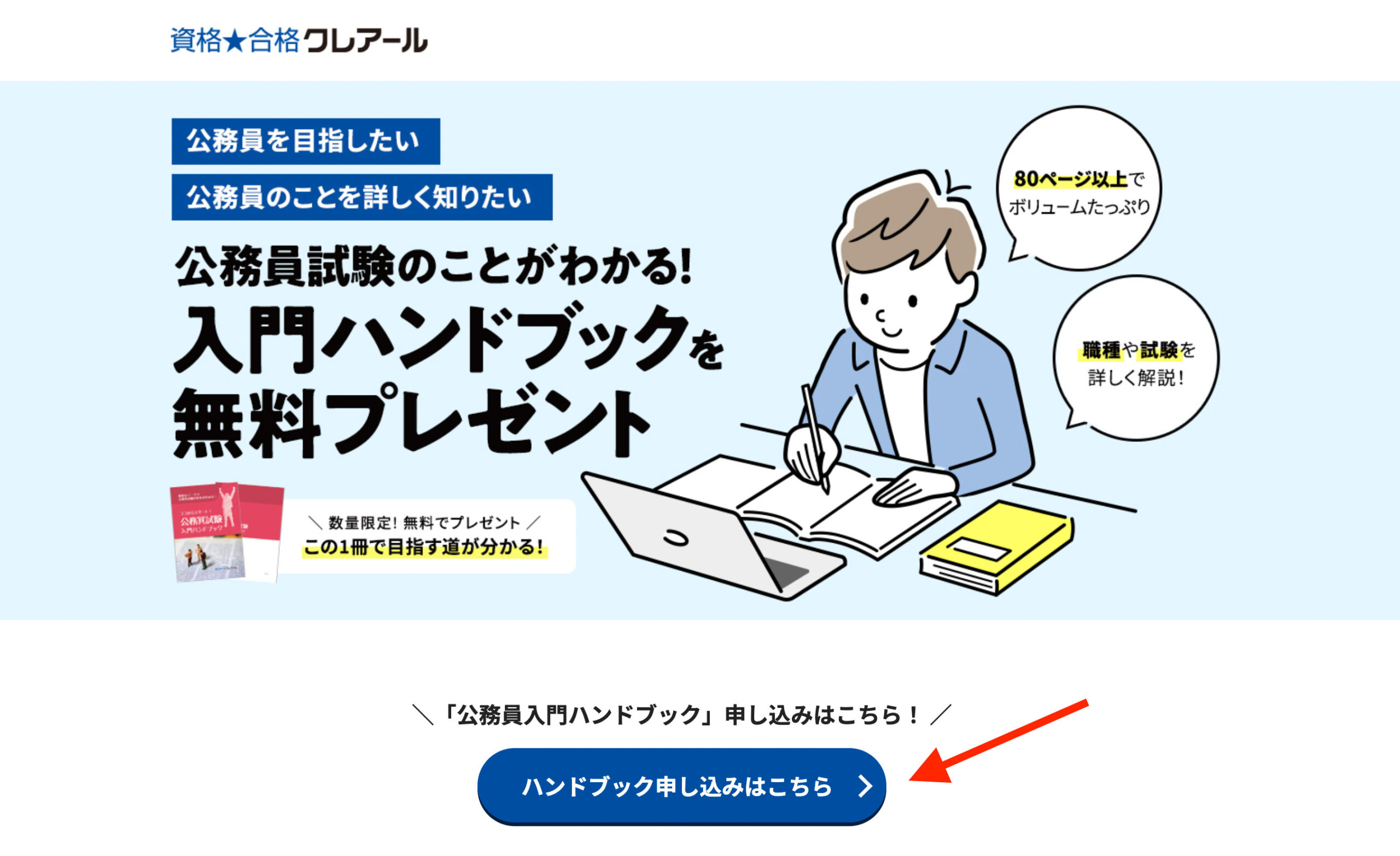
そして「ハンドブック申し込みはこちら」をクリック。
②:必要事項の入力
続いて必要事項を入力していきます。
お名前やメールアドレス、送付先住所などを入力してください。

電話番号は入力しなくても問題ありません。
「勧誘の電話が来たら面倒だな」と不安な方も大丈夫ですよ。
(僕も資料請求しましたが、特に勧誘は来なかったです)
すべて入力したら、確認ボタンをクリックすればOK。
3分もあれば終わるはずです。
※電話番号の入力は任意。しつこい勧誘なし
【まとめ】公務員になるには、まずは「情報収集」から

公務員になりたい人が最初に行うべきことを紹介しました。
何度も言いますが、とにかく「情報収集」から始めてください。
必要な勉強は何か・どこを優先的に勉強すべきか等の戦略が、公務員試験突破には不可欠。
「情報収集」が全ての土台になります。
情報がない状態で勉強すると、ほぼ確実に落ちると思いますね…
情報収集の手段自体は何でもよいです。
ただ「お金をかけたくない」「手間を省いて良質な情報を得たい」なら、公務員試験入門ハンドブックがおすすめ。
無料ですし、もらって損はないと思いますよ。
人間は忘れる生き物です。
「明日やろう」と思っても、確実に忘れます。
公務員になりたい方は、今この瞬間に動き出しましょう。
※電話番号の入力は任意。しつこい勧誘なし